| 「コトタマ学とは」第二百二十二号 平成十八年十一月号 | ||||
先号講座の終りに水蛭子(ひるこ)と淡島(あはしま)の話をしました。水蛭子につきましては詳しくお話申上げましたから御理解を頂けたことと思います。淡島についてはもう少し説明しておいた方がよいように思いますので、少々重複するかも知れませんが、説明を加えることといたします。人間本来の物事の認識作業はウ―ア・ワ―オエ・ヲヱという宇宙剖判の天津磐境の心の構造に則って行われて始めて真実の認識が可能となります。この事は心の先天構造のところで何回も説明して来ました。それに対して淡島と古事記が呼ぶ認識は、主体アと客体ワが対立して出合う所から始まります。アとワの対立から始まる物事の締まりですからアワ島即ち淡島と呼ばれます。人間が大自然から授かった宇宙剖判による判断力である天津磐境によれば、人が処理すべき物事に出合った時、その物事の今までに到る過去の出来事、並びに今・此処の現状(実相)が掌に取る如く見ることが出来ますから、その物事を将来に向ってどの様に処理したらよいか、も立ち所に分かります。誤ることはまずありません。 それに比べて淡島ではどんな内容の判断になるのでしょうか。対立する客体(処理すべき物事)は眼前にある事態です。その過去と現実の内容を見定めるのは、万人共通の天津磐境という天与の判断力ではなく、主体である人間がその時までに心の中に集めて来た経験知識です。となるとどういう動きとなるでしょうか。 主体である人は眼前の事態の内容を自分の経験知識を総動員して観察します。そして「これこれだ」と判断の結果を出します。と同時に、今の事態をどういう結果に導いたらよいかを考えます。今まで一般的に考えられて来た過去の立場を正と呼びます。それに対してその人が観察した現状を反と設定します。すると、その人は今までの考えられて来た立場(正)と自らが判断した状態(反)とを比べて、そのどちらも抱含し、更にどちらをも肯定することが出来る第三の立場を探究し、そこで設定された立場を論理の目的地と定めます。この目的地となる立場を正反に次ぐ合の立場と呼びます。この正と反から合に導く思考法を哲学では正反合の弁証法と呼びます。 右の考え方の内容を簡単に述べますと次のようになります。今まで物事は「これこれ」のように進んで来ました。そこに矛盾が起こり物事は停滞しました(正)。そこで新しい人が選ばれ、考え方を一新しようとしました。その人は自分の立場で物事を観察し、この矛盾を解決するには今までとは異なった立場に立つべきだ、と判断しました(反)。しかし今まで(正)からこれからの(反)に強引に移したら混乱が起こるでしょう。そこで(正)の方からも容認され、更に(反)の内容をも実現する立場を求めて(合)に辿り着きました。事態は新たな動きとなりました。これが正反合の内容です。 新聞・テレビは勿論、幾多のメディアが報道する社会の出来事、議会、官庁、学校、会社、学会等々の運営の方針はすべて右のような正反合弁証法の考え方によって公案され、実施に移されます。社会全体はこの様に運営されています。如何にも合理的で賢(かしこ)い方法と思われることでしょう。民主的社会も独裁的社会も多少の差はあっても似たり寄ったりの方法に変わりはありません。この様に万人が信じて疑わないこの考え方に大きな「落とし穴」があることに、そしてその落とし穴のために、人々は社会の中にあって競い合う論争の渦の中に巻き込まれ、四苦八苦していなければならない事に気付く人は寥々たるものであります。誰も疑っていないのです。今の世界、社会は文字通り“淡島”の独擅場(どくせんじょう)ということが出来ます。 どうしてこの様になってしまったのでしょう。余りに長くなりますので、結論を手短にお話しましょう。淡島には、物事の処理を決定し、推進する原動力となる人間に授けられた創造の意志のリズム、八父韻の自覚が欠如しているのです。八父韻とは物事を創造し、実践して行く根元能力であり、物事を推進する上での時と処と次元を決定する法則でもあります。この能力の欠如、自覚の忘却のために、淡島による会議は、その決定から結論の地点に行き着くまでの時間と処との変化の過程を、詳細に予定表として組むことが出来ず、結論の達成は時間の経過に委ねられることとなります。現代人が”淡島漬け“になっている実状はお分かりになったことと存じます。この社会の矛盾は言霊学(布斗麻邇)の講座が進むにつれて、いよいよ明らかに認識されることでしょう。 古事記の文章を先に進めましょう。 そこで伊耶那岐、伊耶那美の二神は相談をしまして「今、私達が生んだ水蛭子と淡島という子は正式の子供として数に入れるには適当ではありません。こうした事になったからには、高天原の天つ神の処へ行って出来事の全部を申上げて、如何にすべきか聞くことにしましょう」ということになり、高天原に上って行って再び天つ神の命令をお願いしました。報告を聞いた天つ神は布斗麻邇(ふとまに)の原理を参照して「貴方がたは女が先に言葉を発したのが適当でなかったのです。もう一度現象界に下りて行って、その事を改めて発音したらよいでしょう」と命令なさいました。 古事記の文章を現代語に直せば以上のようになります。話の内容については読者の皆様はお分かり頂けていることと思います。岐の命と美の命は言葉を掛け合って結婚に入る前から「女が先立ち言うのは如何なものであろうか」と既に知っていたからであります。けれど物事に失敗したからは何も起こらない0に返るのが一番よい事だ、と高天原・先天に帰ったのであります。そこで天つ神は参照する為に太卜を持ち出しました。太卜について古事記の訳註を見ると「古代の占法(せんぽう)は種々あるが、鹿の肩骨を焼いてヒビの入り方によって占(うらな)うのを重んじ、これは後に亀の甲を焼く事に変わった」と書いております。これは現代の国学者が古代の「太卜」(ふとまに)の意味を知らないがための誤解であります。「ふとまに」とは漢字で布斗麻邇と書かれ、言霊原理の法則全般の事を表わした言葉であります。「ふと」とは二十(ふと)の意。「まに」とは麻邇(まに)即ち真名(まな)で、言霊のことであります。「マニ」は世界語で、キリスト教でmanna(まな)、仏教で摩尼(まに)、ヒンズー教でマヌ、そして日本で麻邇(まに)と呼びます。言霊は全部で五十個ありますが、五十音図でチキシヒの四列の陽音(濁点を付けられる音)二十個の言霊の一音々々の意義を理解し、自覚し得ますと、その人は五十音言霊原理の法則の一切を理解することから、言霊原理全体を代表するものとして布斗麻邇と呼びました。即ち太卜(ふとまに)とはアイウエオ五十音言霊の原理・法則すべてを表わす言葉であります。岐美の二神は高天原の言霊原理に帰って、その原点に立って再び活動を開始することとなります。占うとは裏である心と、表である言葉を縒(よ)り、綯(な)って、行くの意であります。言霊原理隠没後、太卜は訳註にあるが如く、鹿の肩骨を焼いたり、亀の甲を焼いたりする所謂占法のことと思われるようになりました。 古事記の先の文章に移ります。 再び天つ神の命令を受けた伊耶那岐・伊耶那美の神は淤能碁呂島に降りて、以前の如く天の御柱を廻り合い、岐の命がまづ「何と美しいをとめだな」と発言し、その後で美の命が「何とまあ美しいをとこだこと」と言い、再び身を一つにして御子である淡道の穂の狭別の島を生みました。男である父韻を先に、女である母音を後に発音したのですから、間違いなく現象子音言霊が生まれるのか、と思いましたら、違って何と淡道の穂の狭別の島という島が生まれました。これはどういうことなのでしょうか。 それは先天構造の活動によって、後天である三十二の現象子音が生まれる前に、生まれて来る言霊が精神宇宙の中に占める位置を確定しておくこと、更にその言霊の位置の確認によって、逆に精神宇宙の言霊による構造をも明らかにしておこうとする意図が働いたからに他なりません。生まれる子より前に、生まれて来る子の居場所を決定したのであります。そこで初めて生まれた淡道の穂の狭別の島に続く古事記の文章を先に進めることにしましょう。 次に伊予(いよ)の二名(ふたな)の島を生みたまひき。この島は身一つにして面(おも)四つあり。面ごとに名あり。かれ伊予(いよ)の国を愛比売(えひめ)といひ、讃岐(さぬき)の国を飯依比古(いひよりひこ)といひ、粟(あは)の国を、大宜都比売(おほげつひめ)といひ、土左(とさ)の国を建依別(たけよりわけ)といふ。次に隠岐(おき)の三子(みつご)の島を生みたまひき。またの名は天の忍許呂別(おしころわけ)。次に筑紫(つくし)の島を生みたまひき。この島も身一つにして面四つあり。面ごとに名あり。かれ筑紫の国を白日別(しろひわけ)といひ、豊(とよ)の国を豊日別(とよひわけ)といひ、肥の国を建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)といひ、熊曽(くまそ)の国を建日別(たけひわけ)といふ。次に伊岐(いき)の島を生みたまひき。またの名は天比登都柱(あめひとつはしら)といふ。 最初の淡道の穂の狭別の島を入れますと、伊予の二名の島、隠岐の三子の島、筑紫の島、伊岐の島と合計五つの島が生まれて来ます。さて、以上のことを頭に入れておいて、先にお話しました天津磐境(あまついはさか)と呼ばれる心の先天構造を思い出して下さい。この先天構造図は五階層から成立しています。磐境とは五葉坂(いはさか)の意と申上げました。最初から五番目までに生まれた島の名前は、この天津磐境の五階層の言霊の一階層それぞれの位置とマッチして、その位置を決定している島の名前なのであります。図はそのそれぞれを対称として示したものであります。島の名の意味を一つずつ説明して行くことにしましょう。
伊予の二名の島とはイ(ヰ)言霊が自覚・確認される 予 めとなる二つの名の締り、の意。二つの名とは主体と客体アとワに分かれた名であって、分かれたことで思考が可能になります。主と客に分かれなければ思考は出来ません。それ故、二名であるアとワはイ言霊に思考が達するための前提ということになります。「この島は身一つにして」とは言霊アとワは身一つの言霊ウから分かれた事を意味します。「面四つあり」とはアワは宇宙剖判して四つ言霊が現れることをいいます。「伊予(いよ)の国を愛比売(えひめ)といひ」とは、言霊エ(実践智)は経験知オの中から選ばれます。経験知オは実践智エを秘めていることです。即ち伊予の国は言霊オです。「讃岐(さぬき)の国を飯依比古(いひよりひこ)といひ」とは、飯(いひ)とはイの言霊(ひ)のこと。イ言霊を依る(選る)主体(比古)で言霊エです。「粟(あは)の国を、大宜都比売(おほげつひめ)といひ」とは、大宜都比売とは大いによろしき都を秘めているの意。都とは宮(言霊図)の子で言霊、大宜都比売全部で大いに宜しき言霊によって組織されたもの、の意で言霊ヲであります。「土左(とさ)の国を建依別(たけよりわけ)といふ」とは、建(たけ)とは田(た)の気(け)で言霊のこと、それを依り分けた区分(別)の意で言霊ヱとなります。伊予、讃岐、粟、土左の四つの国は四国を表わし、四面に掛けて示したものでありましょう。 「次に隠岐(おき)の三子(みつご)の島を生みたまひき。」隠岐(おき)は隠れた所で先天構造、三子(みつご)は第三段目の島の意。即ち言霊オ、エ、ヲ、ヱ四言霊を指示しています。「またの名は天の忍許呂別(おしころわけ)」とは「天の」は先天のこと、忍許呂別(おしころわけ)とは大いなる(忍)心の(許呂)の区分(別)の意であります。経験知と実践智は先天の働きの中でも傑出した働きであります。 「次に筑紫(つくし)の島を生みたまひき。この島も身一つにして面四つあり。面ごとに名あり。かれ筑紫の国を白日別(しろひわけ)といひ、豊(とよ)の国を豊日別(とよひわけ)といひ、肥の国を建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)といひ、熊曽(くまそ)の国を建日別(たけひわけ)といふ。」「筑紫の島」の筑紫とは尽(つく)くしの意で、人間に与えられた究極根本活動は八つの父韻で表わされ、それで尽くしていることから、八つ四組の父韻を指示します。その四組の父韻を四つの国に割り振って説いております。 「筑紫の国を白日別(しろひわけ)といひ」とは、白日別の白(しら)は父韻シとリの謎、「豊(とよ)の国を豊日別(とよひわけ)といひ」とは豊日別は父韻チとイの呪示、「肥の国を建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)といひ」とは父韻ヒとニの呪示であり、「熊曽(くまそ)の国を建日別(たけひわけ)といふ」とは熊曽の国の熊が父韻キとミを指示していることであります。肥の国については父韻ヒニの説明の項に帰ってお読み下さい。「建日向(たけひむか)」は父韻ヒに、日豊久士比泥別(ひとよくじひねわけ)が父韻ニの神名、妹阿夜訶志古泥(いもあやかしこね)の神と比べればお分かりになりましょう。以上、筑紫の島の面四つについて説明をいたしました。 「次に伊岐(いき)の島を生みたまひき。またの名は天比登都柱(あめひとつはしら)といふ。」 以上で心の先天構造である天津磐境の五段階のそれぞれの段が精神宇宙に占める位置・内容を表わす五つの島についての解説を終わります。さて、ここで改めて申上げておくことがあります。古事記を載せている本の訳註を見ますと、この島生みに登場する島の名前は、現在の日本の地図上にある島の名を取り上げていますが、古事記のそれとは何ら関係がないという事を覚えておいて頂きたいということであります。古事記の編者太安万侶は神々の位置、居所、宝座を示すのに島の名を用いましたが、それはその内容を示すに都合のよい島の名を、実在する島の名の中から便宜上、アトランダムに引用して記載しました。古事記神話の中の島の名は、実際に存在する島とは何ら関係がありません。飽くまで島の名前のみの方便上の引用であります。
日本国の肇国は今より少なくとも八千年余昔のことである。その肇国は力の強いもの、武器の優秀なものを持っていた人達が近隣を武力でもって征服して建てたのではない。言霊の原理を発見し、それを修得した大勢の人々がこの日本列島に上陸し、その保持する言霊の原理に従ってこの国の風土を観察することにより所謂現在の日本語の元となる言葉を造り上げ、その言葉による社会運営の合理性の徳を発揚することによって人々を靡かせ、日本国の肇国となったのである。 言霊の原理を布斗麻邇と言った。また一言(ひとこと)で霊(ひ)とも呼んだ。人の心を分析し、もうこれ以上分析出来ない心の要素五十個を得、それに言葉の要素の五十音とを合理的に結び付け、その一つ一つを言霊と呼んだ。人間の心は五十個の言霊から成り立っていて、それで全部である。人の精神から発する一切の現象の実相を見、その実相に言霊を以って名を付けたのであるから、日本語はそのまま物事の実相を表わす言葉となる。日本を昔から「惟神(かんながら)言挙げせぬ国」と呼ぶ所以である。「物事の実相を言葉がすべて言い尽くしていて、それに説明を加える必要のない国」の意である。 言霊原理を霊(ひ)と呼ぶ。その霊によって造られた日本語が走る(駆[か]る)から日本語を光の言葉と言った。その言葉が走る所、一切の悪は立ち所に消えてしまう。世界の人々はその徳を慕(した)い、世界は霊(ひ)の本の国を中心として人類の第一精神文明時代を創造して行った。日本肇国以来約五千年間の出来事であった。 時は流れた。今より三千年の昔、世界文明創造の中心政庁であった日本の朝廷の中で、文明創造上の方針の大転換が計画された。言霊原理による人類の第一精神文明に次ぐ第二の物質科学文明創造の時代である。精神文明が人間真理を心の内に見る文明とすれば、物質文明は真理を外に探究する文明である。その外なる探究には内なる文明は不要である。今から二千年前、第十代崇神天皇の御宇、言霊原理は政治への適用を廃止され、伊勢神宮の御神体として祀られてしまった。第十五代応神天皇の御宇、日本国の政治運営、文明の社会創造はすべて外国からの輸入の制度、文化に頼る時代となった。日本が唯一日本であるべき根本となる言霊原理と光の言葉である日本語とは外来の信仰と外国語の底に隠没して行ったのである。 時が更に流れた。言霊原理は日本人の記憶からも消えてしまった。日本語の語源は未だに“不明”で片付けられている。ただ「太古の日本は心豊かで、和やかで、精神的に美しかった」という記憶が歴史を通して微かに残っている。その微かな記憶とそれに向けた憧憬の心が明治時代以後の所謂国粋主義の擡頭(たいとう)と繋がっている。国粋主義はよく「美しい日本」「四季の別が明らかで、風光明媚(ふうこうめいび)な日本」という言葉を叫ぶ。そしてその延長上に「愛国精神」を口にするのである。かかる言葉を口走る人々の魂を神道で白狐という。仏教の禅では理屈で悟ったことを吹聴する人を野狐禅と呼ぶ。白狐も同じ、真実の日本を知らず、「日本は美しい、日本国を愛せ」と叫ぶのは白狐に憑依された人の為す業である。真実美しいのは私達日本人の言葉、日本語を造った原典である言霊布斗麻邇の原理なのであり、単なる山川草木、食べ物、着るものの美しさではない。それ故に、国粋主義者の言葉は何処か空虚なのである。…… そんな事を徒然(つれづれ)に考えていたら、ふと祖国を離れて日本で生活している一外人の愛国についての文章が新聞に載っているのを発見した。「私は愛国と国粋とは違うと思う。自分の生まれた国を母国といいます。子供は自分の母親を愛します。母親が美しいとか、料理が上手だから愛するのではなく、自分の母親だから愛するのです。」この心からは国粋主義は出ては来ない。 若し国粋主義が許される事があるとするなら、それは日本人が自らの国家と日本語の発生の基礎である言霊布斗麻邇の学問を自覚し、それに基づいて世界の恒久の平和と繁栄に奉仕する為に立ち上がる時であろう。「そうなったら日本人はそれこそ肩怒らして威張るんじゃないか」って。否、それは正反対なのだ。言霊の学問とは人が自らの心を反省し、親鸞上人がいみじくも言った「煩悩具足の凡夫地獄は一定住家ぞかし」の如く、自分の心根を万人の下積みとして見た人間にして初めて学習出来る学問なのである。 (おわり)
|
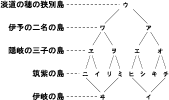 淡道の穂の狭別の島とは、アとワの言霊(穂)へ、狭い所を通って来て、別れて行く島(締めてまとめた区分)の意。「狭い所を通って来て」とは何もない宇宙の一点から現象の兆(きざし)として生れ出ようとするもの(言霊ウ)が次の瞬間、アとワの主体と客体に別れんとする位置にある言霊、と言った意味であります。これは正しく天の御中主の神(言霊ウ)のことです。
淡道の穂の狭別の島とは、アとワの言霊(穂)へ、狭い所を通って来て、別れて行く島(締めてまとめた区分)の意。「狭い所を通って来て」とは何もない宇宙の一点から現象の兆(きざし)として生れ出ようとするもの(言霊ウ)が次の瞬間、アとワの主体と客体に別れんとする位置にある言霊、と言った意味であります。これは正しく天の御中主の神(言霊ウ)のことです。