| 「コトタマ学とは」第二百十九号 平成十八年九月号 | |||
前回の講座で八つ、四組の父韻の中のチイ・キミの四つ、二組の父韻について説明を終えました。今回はシリ・ヒニの四父韻について説明してまいります。 意富斗能地(おほとのぢ)の神・父韻シ、妹大斗乃弁(いも・おほとのべ)の神・父韻リ 理屈ポクって理解し難いと言う方もいらっしゃると思います。そこで平易な例を引きましょう。毎週月曜夜八時、6チャンネルと言えば、直ぐに「水戸黄門」と気付く方は多いことでしょう。このドラマの前半は悪家老、代官が悪商人と組んだ悪事の描写です。後半はそろそろ黄門様一行がその悪事の真相に近づいて行きます。ここまでは毎回新しい脚色が工夫されています。けれど最後の数分間は何時も、数十年にわたって変わらぬ結末が待っています。 最後に悪人一味の悪事が暴露されると、悪人達は老公一行に暴力を行使しようとします。すると御老公は「助さん、格さん、懲(こら)らしめてやりなさい」と命じます。善悪入り乱れてのチャンバラとなり、老公の「もうこの位でいいでしょう」の言葉と共に、助さん(または格さん)が懐の三つ葉葵の印籠(いんろう)を取り出し「静まれ、静まれ、この印籠が目に入らぬか」と悪人達の前にかざす。そこで一件落着となります。
次に妹大斗乃弁の神・父韻リの説明に入ります。大斗乃弁とは、漢字の解釈から見ますと大いなる量(はかり)のわきまえ(弁)と見ることが出来ます。また神名に妹の一字が冠されていますから、意富斗能地(おほとのぢ)とは陰陽、作用・反作用の関係にあることが分かります。この事から推察しますと、父韻シリは図の如き関係にあることが分かって来ます。五十音図のラ行の音には螺理縷癘炉(よりるれろ)等、心や物質空間を螺旋状に広がって行く様の字が多いことです。そこでこの図の示す内容を理解することが出来ましょう。 「風が吹くと桶屋が儲かる」の譬えがあります。風が吹くという一事から話が四方八方に広がって行き、最後に桶屋が儲かるということに落ち着くのですが、ここで落ち着かないで、更に諸(もろもろ)が発展して行き、永遠に続くことも可能です。人の考える理屈が野放図に広がって行く譬えに使われています。これも父韻リの説明には不可欠の理屈の働きと言えましょう。また噂(うわさ)に尾鰭(おひれ)がつく、という言葉があります。一つの噂に他人の好奇心による単なる根も葉もない推察が次々と加えられ、当事者や、または全然関係のない大勢の人々に間違った情報が伝わって行くことがあります。時にはそれが社会不安を惹き起こしたり、大きな国家間の戦争の原因になることがあります。これ等の現象は人間の心の中の父韻リが原動力となったものであります。原油価格の高騰が伝えられた数日後、スーパーマーケットの店頭からトイレットペーパーが姿を消してしまったという話をまだ記憶に留めていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 父韻リの働きを説明するために悪い影響の話ばかりして来ましたが、父韻リには善悪の別は全くありません。人間誰しもが平等に授かっている根本能力の一つであります。発明家といわれる人は、一つの発想、思い付きから次から次へと新しい発明品を発表して行きます。これも父韻リの原動力によるものであります。この根本力動の韻律によって人類は現在ある如き物質文明を建設して来たのでもあります。 於母陀流(おもだる)の神・父韻ヒ、妹阿夜訶志古泥(いも・あやかしこね)の神・父韻ニ では「心の表面に言葉が完成する韻(ひびき)」とはどういうことなのでしょうか。言い換えますと、心の表面に言葉を完成させる原動力の火花とはどういう事を言っているのでしょうか。例を挙げることにしましょう。或る会社の創立三十周年の祝賀会に招待されて出席しました。盛会でありましたが、その席上、突然ある人から声をかけられました。「M会社の中村さんですな。あの折には種々お世話になり有難う御座いました。その後ご無沙汰申上げて申訳御座いません。改めて御挨拶にお伺いさせて頂こうと思います。その折はよろしく御願い申上げます。」そこまで話が来た時、その人は同席の同じ会社の人と思われる人に促(うなが)されて、「では失礼いたします」と去って行ってしまいました。自分だけしゃべって、名前も言わずに行ってしまって、無作法な人だなと思ったのですが、その人の名前を思い出せません。何処で会ったかも分かりません。けれど一度会った人であることは間違いないようです。さあ、こうなると、その人のことが気になって仕方がありません。「何処で会った人なのかな」「何という名前だったかな」考えてみても喉(のど)に引っ掛かったように答えが出て来ません。家に帰ってきてからも同じような気持で、何となく今にも思い出せそうでいて、出て来ません。翌朝、会社に出ようと靴を履こうとした時、ハッと思い出しました。「あっ、そうだった。二年程前の会社の後輩の結婚式の披露宴の席上、テーブルの隣の席にいたN販売の木村さんだ。披露宴の酒が進み、座が少々乱れ出した時、あの人と仕事のことでいろいろ話した事があった。あの人はそのことを言っているのだ。」喉につっかえていたものが一遍に吐き出された気持でした。「仕事でない所で会ったので、記憶が薄れてしまったのだ」と思ったのです。 例の話が少々長くなりました。父韻ヒの韻律をお分かりいただけたでしょうか。言葉が胸元まで出て来ているようで、喉元に引っ掛かって出て来ないもどかしい気持がフッと吹っ切れて、口というか、頭の表面というか、心の表面とも言える所で、記憶がハッキリした言葉となって完成する、否、完成させる言動韻、これが父韻ヒであります。 次に妹阿夜訶志古泥(いも・あやかしこね)の神・父韻ニの説明に入ります。先ずは神名の漢字の解釈から始めましょう。阿夜訶志古泥の阿夜は「あゝ、本当に」の古代の感嘆詞。訶志古泥(かしこね)は賢(かしこ)い音(ね)の意です。神名をこのように解釈した上で、先の於母陀流(おもだる)が面足と言葉が心の表面にパッと完成する原動韻であり、それと阿夜訶志古泥が陰陽、作用・反作用の関係にあることから考慮しますと、阿夜訶志古泥は「心の中心に物事の発想や記憶の内容が煮詰(につ)まってくる原動韻」と推定することが出来ます。心の中心に於ける現象なので阿夜と夜という字が用いられ、暗い所という意味を強調しています。この原動韻が父韻ニであります。 この状況を、前の於母陀流の神の説明の例をもう一度振り返ってお話してみましょう。自分の名も告げずに「M会社の中村さんですな。ご無沙汰しております。」と話しかけて、そのまま去って行った人を、「誰だったか、何処であった人か、……」と直ぐにも思い出しそうで思い出せない。そのままその日は終り、翌朝になってやっと「N販売の木村さんと言ったな」と気付いた時、念頭に相手の名前が浮かんだ時、その時には既に「二年程前に披露宴で隣の席にいた人、どんな話をしたか」の記憶が蘇えっていた筈です。心の表面に相手の名前が「木村さんと言ったな」と言葉が完成した時(父韻ヒ)、心の中では披露宴の状況も煮詰まっていたのです。これが父韻ニということになります。父韻ヒと父韻ニは確かに陰陽、作用・反作用の関係にあることが確認されます。 以上で八つの父韻のそれぞれについての説明を終ります。八つの父韻は四つの母音宇宙を刺激することによって、一切の現象即ち森羅万象を生みます。人類に与えられた最高の機能ということが出来ましょう。神倭王朝第十代崇神天皇以後二千年間、今日に到るまで、誰一人として口にすることなく時は過ぎて来ました。ただその存在は儒教に於て「八卦」、仏教に於て八正道、あるいは「石橋」という言葉で、またキリスト教では神と人との間に交(か)わされた契約の虹(にじ)として語られて来たにすぎません。今、此処に八つの父韻が名実共に明らかになった事は、この父韻だけを取上げただけでも、人類の第一、第二文明を過ぎて、第三の輝かしい時代の到来を告げる狼煙(のろし)とも言うことが出来るでありましょう。人類に授けられた森羅万象創生の機能は父韻チイ、キミ、シリ、ヒニの八つです。たった八つであり、八つより多くも少なくもありません。この八つの父韻を心中に活動させて、人類は一切の文明を永遠に創造して行くのであります。
ひかりの話をしましょう。私が初めてひかりを見たのは、否、ひかりに対面しましたのは、今から四十年前の春遅い頃と記憶します。所は茨城県西部、下妻市の西境を流れる鬼怒川の河川敷でありました。私はその頃、言霊学の師、小笠原孝次氏を離れて一人で仏教の禅宗の「色即是空、空即是色」の修業のために、大自然の中に身を置いて坐禅の最中でありました。来る日も来る日も一人ポツンと河川敷に坐り、ジッと空とは何ぞや、我とは何か、を考える日々でありました。これを始めて半年が経ちます。疲れが出て来ました。まだ何の成果もありません。万策尽きて来ました。絶望感が時々顔を出します。その時です、有り得ないことが我が身に起こったのは……。 突然、鳩尾(みぞおち)の所がグイッグイッと下から突き上げられます。同時に視点がグングン高くなって行き、少なくとも数百メートル上空に上がりました。そこから見る光景は正に絶景です。鬼怒川の遥か上流から下流にかけて田や畠や森が見渡せます。その中を川が北から南へ真直ぐに流れているのが見えます。そして下を見ると、河川敷に坐る自分の姿が小さく見えるではありませんか。そして何より驚いたことには、私を取り巻く大気がすべて光の粒なのです。細(こまか)いおだやかな、何とも言えないなごやかな光の粒なのです……。こんな状態がどの位の間続いたのでしょうか。多分二十分以上であったと思われます。そしてふと気が付くと私は元の河川敷に坐っている自分の中に帰っていました。そして何事もなかったかの如く、「禅宗無門関」という本を手にして、何時もの自分でありました。夢かな、と思いました。けれど夢では決してありません。何故なら、自分の身に起こった一部始終を完全に醒めた目で見たはっきりした意識の繋がりを持っていたことです。そしてその夜遅くなるまで、佛の光に包まれている幸福感に満たされて、心温かな自分であり、その時までに知り合った人々が皆、兄弟同胞の如く思えたことを覚えております。 さて、この思ってもみなかった体験を自分の勉学の途上、どのように考えたらよいのか、皆目分かりません。気が狂ったとも思えません。「矢張り先生に尋ねるより他はない」と思い、翌朝一番の電車で上京し、渋谷、幡ヶ谷のお宅に伺いました。先生は懇切に教えて下さいました。 「仏教の浄土三部経の中の阿弥陀経に青色青光、黄色黄光、赤色赤光、白色白光とあり、目で青い色と見えるものは、実は青い光なのであり、黄いろい色と見えるものは、実は黄いろい光なのであり……世の中はすべてそれ等の光で出来ているのです。この光を仏教は寂光といい、無礙光(むげこう)といい、この世の中は実はこれ等の光によって構成されているのです。それが物事の実相というものです。貴方は熱心に求めていたから、佛が、即ち人間の生命そのものが、それを認め、求道をはげます意図で、その光を垣間(かいま)見せて頂いたというわけです。光を見たからといって、威張ることも、自分が特殊な人間だと思うこともありません。誰でも見ていることなのです。生まれたばかりの赤ん坊は、まだ視力がないと言われる時、その円(つぶ)らな瞳で空中を見ているのをご存知でしょう。あの時、赤ん坊はこの無礙光、寂光を見ているのです。大きく成長して“自我”意識が芽生えると同時に見えなくなってしまいます。また光を見ることが出来た人も、光の内容を知る正しい道、即ち声聞から阿羅漢、菩薩、仏陀の道を歩み出すと同時に見なくなります。その道が諸法実相の誠の道ですから、もう垣間見る必要がないからです。言霊学で謂うなら、言霊ウオアエイの天之御柱の自覚の道へ進めば光は見なくなります。光の示す実際の生活に入るからです。……」 そして先生は笑いながら次のように言葉を継ぎました。「何故そんな奇蹟のようなことを見せられたか、ですか。それは貴方が我(が)が強く、煩悩熾盛(しじょう)で、怠け者だから、お道に辿りつくのは容易ではなかろうと心配して下さって、仏様が貴方の目的地はこんなに素晴らしい処なのだよ、と予め知らせて、決心を鈍らせないように励まして下さったからでしょう。ハッハッハッ……」とお笑いになったのを覚えております。そして「この後の勉強には法華経をお読みになっておいた方がよいでしょう。貴方の質問の答えはお経の中にすべて書いてあります。」と教えて下さいました。 私は岩波文庫本の「法華経」上中下三巻を買い、貪(むさぼ)るように読んでみました。法華経二十八品の中の方便品(ほうべんぼん)と化城喩品(けじょうひぽん)では光を垣間見る境地のことを、「それは仏が求道者のために方便で設けた幻(まぼろし)の世界であり、真実の道を求める人はそこに安住せず、人生第一義の境地を求めて勇躍して進むべし」と説き、「仏の道とは仏所護念(仏が自覚して常に念じる道)であり、教菩薩法(菩薩を教える原理)の事である」と示しています。私は法華経によって仏教とは仏が教える教えであって、「仏とは何ぞや」を教えてはいない事を知ったのであります。と同時に人類最高の教えとは、日本民族一万年の伝統の学アイエオウ五十音言霊布斗麻邇古神道なのであることを深く肝に銘じたのであります。 一九八二年、二十年間言霊学を教えて下さった小笠原孝次先生が七十九歳で逝去されました。亡くなる一ヶ月前、私に後事を託され、特に古事記神話の最終結論である禊祓の詳細な解釈を宿題として頂きました。五年間の準備の後、私は言霊学研究と普及の活動を始めるため一九八七年七月、言霊の会を創設しました。言霊学の普及のため会報の出版と同時に先師よりの宿題である古事記言霊百神の中の八十一番目、奥疎(おきさかる)の神から神名一つ一つを丹念に自分の心の中に探す作業に入りました。希望と絶望を積み重ねる探究の連続でありました。またたく間に十八年の歳月が過ぎました。二○○六年の春、探究は漸く神直毘(おむなほひ)、大直毘(おほなほひ)、伊豆能売(いづのめ)の三神の所に入っていました。この三神を越せば、以後の神々の内容は略々分かっています。勇み立ちました。けれどこの三神を私の中に見つけることは至難の業であることが分かって来ました。この至難の業という事を説明するために古事記の文章を少々引いてみましょう。 ここに詔りたまはく、「上つ瀬は瀬速し、下つ瀬は弱し」と詔りたまひて、初めて中つ瀬に堕り潜きて、滌ぎたまふ時に成りませる神の名は、八十禍津日(やそまがつひ)の神。次に大禍津日(おほまがつひ)の神。この二神(ふたはしら)は、かの穢(きたな)き繁(し)き国に到りたまひし時の、汚垢(けがれ)によりて成りませる神なり。次にその禍を直さむとして成りませる神の名は、神直毘の神。次に大直毘の神。次に伊豆能売。 禊祓とは外国の文化を吸収し、それに生命の息吹を与え、そのままの内容で世界文明創造の糧にすることです。それには議論も宗教的恩恵も必要ありません。唯ただ明るい生命の言葉があるだけなのです。八十禍津日とは宗教の恩赦であり、大禍津日とは哲学的理論による止揚(しよう)・揚棄なのです。(止揚=弁証法的考え方で、矛盾対立する二つの要素(概念)に関連して両者を否定し、しかも一段と高い統一体に発展させること)そのことを古事記は「この二神は、かの穢き繁き国に到りたまひし時の、汚垢によりて成りませる神なり」と、指摘します。そして「その禍(まが)を直さむとして」とハッキリ言い切っています。これより先は一切の禍は通れませんよ、とシャットアウトしています。現代人が背負っている一切の天津罪、国津罪があれば、心の中にこの三神を見つけることは出来ませんよ、と「通行止」の立札を立てているのです。呆然と立ち竦(すく)んでしまいました。善い点など挙げるのは骨が折れますが、悪い点なら両手の指を何回も折る程ある身が一点の曇りも赦されない生命そのものの次元に入ることなど出来よう筈もない。他人事だと思って読んでいた歎異抄の親鸞の言葉「煩悩具足の凡夫、地獄は一定住家ぞかし」が他ならぬ私の身であったのです。頭を抱えこんで、のた打ち回る日々が続きました。 そんなある日、空いっぱいの雲の間に隙間が出来たのでしょうか、または地獄の底でのたうち廻る私を、皇祖皇宗が「哀れ」と思し召して、地獄の底に御手を差し伸べて下さったのでしょうか。一瞬、心の扉が開け、四つの母音(アオウエ)、三つの半母音(ワヲヱ)、三十二の子音が、生命の創造意志イ・ヰの息チイキミシリヒニの韻律につれて、それぞれの言霊独特の色彩の言葉が流暢に頭の中から飛び出して来たのでした。それはある一つの事件への絶対命令でありました。私が、置かれた立場の真相を把握した上で、その状態から解決の方向へ事態を動かす筋道が丹念に計算されるものの如く、実相として画かれて行く言葉の連(つら)なりでありました。この言葉によって、神直毘・大直毘・伊豆能売三神の内容を私の心の中に見つけることが出来たのです。言霊アの光は寂光と呼び、無礙光といいます。言霊イ・エの光は言霊五十音が発する五十種類の実相の光の言葉なのだということを知ったのでした。言霊百神はすべて人の心の中に見つける事が出来るようになりました。 (以下次号) |
 三種の神器の第二は「八坂の曲玉(やさかのまがたま)」です。曲玉とは丸い玉でなく、玉に尾が生えたように巴形になったものをいいます(図参照)。八坂の曲玉は玉の真中に穴を開け、幾つもの玉を集めて紐を通して数珠(じゅず)(ロザリオ)にしたものです。曲玉とは、またそれを数珠にしたことは、何を表徴しているのでしょうか。
三種の神器の第二は「八坂の曲玉(やさかのまがたま)」です。曲玉とは丸い玉でなく、玉に尾が生えたように巴形になったものをいいます(図参照)。八坂の曲玉は玉の真中に穴を開け、幾つもの玉を集めて紐を通して数珠(じゅず)(ロザリオ)にしたものです。曲玉とは、またそれを数珠にしたことは、何を表徴しているのでしょうか。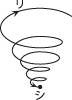 この印籠の出現の前に、事件に関わったすべての人々の意志、動向が静まり、御老公の鶴の一声によって結末を迎えます。この一点に騒動がスーッと静まり返る韻、これが意富斗能地の父韻シであります。この大きな入り乱れてのチャンバラが、御老公の三つ葉葵の印籠の一点にスーッと吸込まれて行くように収拾されて行く働き、それが父韻シであります。水の入った壜(びん)を栓を抜いて逆(さか)さにすると水は壜の中で渦を巻いて壜の口から流れ出ます。父韻シの働きに似ています。この渦の出来るのは地球の引力のためと聞きました。水は螺旋状に一つの出口に向って殺到しているように見えます。父韻シの働きを説明する好材料と思えます。
この印籠の出現の前に、事件に関わったすべての人々の意志、動向が静まり、御老公の鶴の一声によって結末を迎えます。この一点に騒動がスーッと静まり返る韻、これが意富斗能地の父韻シであります。この大きな入り乱れてのチャンバラが、御老公の三つ葉葵の印籠の一点にスーッと吸込まれて行くように収拾されて行く働き、それが父韻シであります。水の入った壜(びん)を栓を抜いて逆(さか)さにすると水は壜の中で渦を巻いて壜の口から流れ出ます。父韻シの働きに似ています。この渦の出来るのは地球の引力のためと聞きました。水は螺旋状に一つの出口に向って殺到しているように見えます。父韻シの働きを説明する好材料と思えます。