| 「古事記と言霊」講座 その九 <第百六十八号>平成十四年六月号 | |
古事記の文章を先に進めます。 古事記神話が先天十七言霊全部の出現で人間精神の先天の構造がすべて明らかとなり、言霊学を解説する視点が先天構造から後天構造へ下りて来ました。ここで後天現象の単位である現象子音言霊の誕生の話に移ることとなります。先にお話しましたようにアオウエ四母音とチイキミシリヒニ八父韻の結びで計三十二の子音誕生となる訳でありますが、古事記はここで直ぐに子音創生の話に入らず、創生の失敗談や、創生した子音が占める宇宙の場所(位置)等の話が挿入されます。古事記の神話が言霊学の原理の教科書だという事からすると、何ともまどろこしいように思えますが、実はその創生の失敗談や言霊の位置の話が言霊の立場から見た人類の歴史や、社会に現出して来る人間の種々の考え方、また言霊学原理の理解の上などで大層役立つ事になるのであります。その内容は話が進むにつれて明らかとなって行きます。 吾が身は成り成りて、成り合はぬところ一処あり 伊耶那岐の命が伊耶那美の命に「汝が身はいかに成れる」と問うたのに対し、美の命が「吾が身は成り成りて、成り合わぬところ一処あり」と答えました。「成る」は「鳴る」と謎を解くと言霊学の意味が解ります。アオウエ四母音はそれを発音してみると、息の続く限り声を出してもアはアーーであり、オはオーーと同じ音が続き、母音・半母音以外の音の如く成り合うことがありません。その事を生殖作用に於ける女陰の形「成り合はぬ」に譬えたのであります。 我が身は成り成りて、成り余れるところ一処あり。 この吾が身の成り余れる処を、汝が身の成り合わぬ処に刺し塞ぎて、国土生み成さむ。 人間智性の根本リズムである言霊父韻と、精神宇宙の実在である母音言霊との結合で生れた、現象の実相を表わす単位である子音言霊を組み合わせて作られた日本語は、その言葉そのものが物事のまぎれもない真実の姿を表わす事となるという、世界で唯一つの言葉なのであるという事を、その言語を今も尚話すことによって生活を営んでいる現代の日本人が一日も早く自覚して頂き度いと希望するものであります。 伊耶那岐の命詔りたまひしく、「然らば吾と汝と、この天之御柱を行き廻り逢ひて、美斗の麻具波比せむ」とのりたまひき。 八つの父韻は陰陽、作用・反作用の二つ一組の四組より成っています。即ちチイ・キミ・シリ・ヒニの四組です。伊耶那岐と伊耶那美が天の御柱を左と右の反対方向に廻り合うという事になりますと、左は霊足(ひた)りで陽、右は身切(みき)りで陰という事になり、伊耶那岐は左廻りで八父韻の陽であるチキシヒを分担し、伊耶那美は右廻りで八父韻の陰であるイミリニを分担していると言うことが出来ます。 汝は右より廻り逢へ、我は左より廻り逢わむ。 女人先だち言へるはふさはず 然れども隠処に興して子水蛭子を生みたまひき。 言霊の原理が世の中から隠没した後、言霊学に代わる人類の精神の拠所となる各種の個人救済の小乗信仰の事をいうのであります。言霊の原理は人類歴史創造の規範です。その原理が隠されて、その間に現われた個人救済の信仰、例えば仏儒耶等の信仰は、「人間とは何か」「心の安心とは」「幸福とは」等々、人間の心の救済は説いても、人類の歴史創造についての方策に関しては何一つ言挙げしません。否、言挙げする事が出来ません。現在の地球上の人類生存の危機が叫ばれている昨今、世界の宗教団体から何一つ有効な提言が出されない事がそれを良く物語っています。 世界の大宗教がその点に盲目な原因は、人間の生命創造の根本英智である言霊八父韻と、それによって生れる現象の要素である三十二の子音言霊の認識を全く欠いているからに他なりません。しかし言霊原理隠没の時代には、信仰心に見えるように生命の実在である宇宙(空)とか、救われを先にし、社会・国家・世界の建設等の創造を捨象してしまう事も、即ち母音を先にし、父韻を後にする発声が示す精神行為も時には必要となるであろう事を、古事記の撰者太安万侶は充分知っていたからに他なりません。 「隠処に興して」の隠処とは「組むところ」の意。頭脳内で言葉が組まれる所のことで、組む所は意識で捉えることが出来ない隠れた所でありますので、隠処と「隠」の字が使われています。では実際には言葉は何処で組まれるのでしょうか。それは子音創生の所で明確に指摘されます。言霊学が人間の言葉と心に関する一切を解明した学問であるという事は此処に於ても証明されるのであります。 この子は葦船に入れて流し去りつ。 次に淡島を生みたまひき。こも子の例に入らず。 ところが淡(あわ)島のアとワは、頭脳内の心の先天構造の動きである「宇宙→ウ→ア・ワ」の過程をネグレクトして、主体である自分と客体である現象とに別れた所から思考が始まる事なのです。ですから淡島の心の運びは天津磐境と呼ばれる人間の心の運びの原則とは全く異なる思考方法となります。(この事については「思うと考えるという事」の章に詳しく説明しました。)この事から現象(客体)に対する我(主体)とは先天構造の中の純粋な主体を表わす言霊アではなく、その人の自我、即ちその人自身の経験・知識等の集積である自我であるという事になります。そのため、自我が見る対象の現象は実相を現わす事がなく、自我という経験知識が問いかけた問に対してだけに答えるものとなります。概念による思考形式が此処から始まります。その結論は物事の実相を表わす事が出来ません。淡島即ち実相が淡くしか見えぬ心の締まりと呼ばれる所以であります。これも人間の心の正統な子の数に入れません。 ここに二柱の神議(はか)りたまひて、「今、吾が生める子ふさわず。なほうべ天つ神の御所(みもと)に白(まを)さな」とのりたまひて、すなはち共に参(ま)ゐ上がりて、天つ神の命を請ひたまひき。ここに天つ神の命以ちて、太卜(ふとまに)に卜(うら)へてのりたまひしく、「女(おみな)の先立ち言ひしに因りてふさはず、また還り降りて改め言へ」とのりたまひき。 右は伊耶那岐・美二神の失敗に続き天つ神へお伺いを立てる話でありますが、これを言霊学の教科書としての文章に置き換える必要があります。「太卜に卜へて」とは「布斗麻邇の原理に則って」という事です。そこで右の文章は左の通りとなります。「母音を先に、父韻を後に発音しては現象子音を生むのにふさわしくなかった。だから初めの心の先天構造の天津磐境の原理に帰って検討をしよう。そう気がついて改めて布斗麻邇に照らし合わせてみると『母音を先に発音するのがいけなかった。また後天現象の立場に帰り、再びやり直して今度は父韻を先にし、母音を後にするやり方にしよう』と気付いたのでした」となります。 太古、日本人の祖先が心と言葉の完全法則である言霊布斗麻邇を発見・自覚するまでには幾多の苦心と紆余曲折があったことでしょう。右の古事記の文章はその苦心談の一つと考えることが出来ます。そして行為がうまく行かず、迷った時には早く出発点にもどり、出直してみることが大切であると教えているようにも思えます。尚「太卜に卜へて」を辞書で見ると、「神代に行われた一種の占法。鹿の片骨を焼き、その裂けた骨のあやによって吉凶を占ったものという」とあります。これは二千年前、崇神天皇の御宇、言霊原理が世の表面から隠されて以来、物事を心の原理に基づいて判断する事が出来なくなった為に、その穴埋めに用いられた占(うらない)であります。うらないの語源は裏綯(うらな)うで、現実と裏(心)をより合わせて、物事の先行きを決める、という事であります。 古事記の文章を先に進めます。 最初の子生みに失敗した岐・美二神は、心の先天構造の法則に立ち返り、今度は間違いないやり方で子を生むこととなります。伊耶那岐の命が先に「あなにやし、えをとめを」と言い、その後で伊耶那美の命が「あなにやし、えをとこを」と言います。そして二人の命は交わり合って、淡路の穂の狭別の島を生みました。子を生むと言いながら何故初めに島を生んだのでしょうか。 先天構造を構成する十七言霊の活動によって今後次々と三十二の子音を指示する三十二の神々が誕生して来ます。更に古事記は生れ出た言霊を整理し、それを操作することによって壮大な人間精神の先天と後天の全構造とその動きを明らかにして行きます。その結果、先天と後天の言霊数合計五十、その五十の言霊の整理、操作の典型的な動き方合計五十、総合計百の心の道理を明らかに示す事となります。更に子音言霊やその後の整理・活用を示す神々の名をただ無造作に生み出すのではなく、その生み出す順序と、それを整理する為の明確な区分を前もって明らかにして置く必要があります。即ちその言霊と整理の区分を島の名を以て示そうとする訳であります。言霊の区分と整理活動が心の宇宙に占める位置と区分を島の名によって前以て定めておこうとする作業が始まります。 島とは以前にもお話しましたように「締めてまとめる」の意であります。商店で夕方に帳簿を締めたといえば、それは今日の会計はここで終りとして、明日の会計との区別をつけた、ということです。今日の会計をここで締めて、まとめた訳です。古事記が今から創生する島々も、言霊五十神、その整理法五十神が次々と生まれて来る時に、この神からあの神まではかくかくの内容を持った言霊だ、と内容別に締めてまとめた事であります。 古事記神話に於て伊耶那岐・美の二命によって全部で十四の島々が生まれます。古事記の言霊百神を示す物語が「天地初発の時」より、言霊学原理の總結論である天照大神・月読命・須佐男命(三貴子)(みはしらのうずみこ)誕生までの小説だと喩えるならば、それは島の数十四の章を持った壮大な真理を黙示した物語小説であり、ドラマに喩えるならば、全部で十四幕にまとめられた神々の天上のドラマとなり、これを交響楽に喩えるなら、全章が十四楽章に分れた大シンフォニーなのであります。かく申上げることが出来ますように、古事記の神話は十四段に分れた物語であり、その一段々々が人間精神の働きの部分々々を明確に表現しながら、更にその十四段の全部が水の流れる如くに関連し合って人間の精神生命の全貌を残らず解明し尽くした精神学の完成品だという事が出来ます。 この神話の一節についてもう一つ話を添えて置きたい事があります。岐美二神はお互いに「あなにやしえをとめを」「あなにやしえをとこを」と愛情の言葉を掛けてから天之御柱を往き廻り子音を生みます。この愛情表現は何を示そうとしたのでしょうか。これから生まれて来るものは現象の実相の単位を表わす子音言霊であります。現象の実相は見る人が言霊母音アの次元(そこより感情が生まれる)に視点を置く時、最も明らかに見得るのであります。それ故現象子音創生の前に愛情表現を差し挟んだに違いありません。 子淡路(こあわじ)の穂(ほ)の狭別(さわけ)の島を生みたまひき。 次に伊予の二名(ふたな)の島を生みたまひき。この島は身一つにして面四つあり。面ごとに名あり。かれ伊予の国を愛比売(えひめ)といひ、讃岐の国を飯依比古(いいよりひこ)といひ、粟(あわ)の国を、大宜都比売(おほげつひめ)といひ、土左(とさ)の国を建依別(たけよりわけ)といふ。次に隠岐(おき)の三子(みつご)の島を生みたまひき。またの名は天の忍許呂別(おしころわけ)。次に筑紫(つくし)の島を生みたまひき。この島も身一つにして面四つあり。面ごとに名あり。かれ筑紫の国を白日別(しらひわけ)といひ、豊(とよ)の国を豊日別(とよひわけ)といひ、肥(ひ)の国を建日向日豊久士比泥別(たけひわけひとわくじひわけ)といひ、熊曽(くまそ)の国を建日別といふ。次に伊岐(いき)の島を生みたまひき。またの名は天比登都柱(あめひとつはしら)といふ。次に津(つ)島を生みたまひき。またの名は天(あめ)の狭手依比売(さでよりひめ)といふ。次に佐渡(さど)の島を生みたまひき。次に大倭豊秋津(おほやまととよあきつ)島を生みたまひき。またの名は天(あま)つ御虚空豊秋津根別(もそらとよあきつねわけ)といふ。かれこの八島のまづ生まれしに因りて、大八島国(おほやしまくに)といふ。 (次号に続く)
心と体が一つになったものが生命であるのではない。生命が先ずあって、そこに人間の思惟が加わる時、生命が心と体に分かれるのである。分けるから分る。分けなければ永遠に分らない。これが人間の思惟の持つ業(ごう)である。主体である心と客体である体を両方向に調べ、共に究極の構造に到達した時、初めてその構造が掌の表と裏として相似形を成す事が分る。この時、主と客双方の真理を踏まえ、心の原理である言霊の次元イ(親音)の自覚に立つ時、心と体を両輪とした生命それ自体を観想によって知る事が出来る。生命が生命を知るのである。古事記は伊耶那岐の大神と呼ぶ。 |
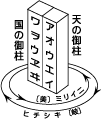 ましたように相対的に双方が離れて対立する場合と、絶対的に主体(岐)と客体(美)とが一つとなって働く場合があります。今、この文章で伊耶那岐と伊耶那美が天の御柱を左と右から「行き廻り合う」という時には図の如く絶対的な立場と考えられます。その場合の天の御柱とは、実は天の御柱と国の御柱とが一体となっている絶対的立場を言っているのだとご承知下さい。
ましたように相対的に双方が離れて対立する場合と、絶対的に主体(岐)と客体(美)とが一つとなって働く場合があります。今、この文章で伊耶那岐と伊耶那美が天の御柱を左と右から「行き廻り合う」という時には図の如く絶対的な立場と考えられます。その場合の天の御柱とは、実は天の御柱と国の御柱とが一体となっている絶対的立場を言っているのだとご承知下さい。